はじめに:その優待、もっと賢く手に入れませんか?
企業の株を持っていると、お礼として自社製品や食事券などがもらえる「株主優待」。これは、株式投資の大きな楽しみの一つですよね。現金でもらう配当金とは違い、おいしい食品やお得な割引券といった形で届くので、生活がちょっと豊かになる嬉しいプレゼントです。
この株主優待を手に入れる一番シンプルな方法は、普通に株を買って持ち続けることです。でも、この方法には「株価が下がって損をするかもしれない」という心配がつきまといます。特に、人気の優待株は「この日までに株を持っていれば優待がもらえますよ」という締切日に向けて値段が上がり、締切日を過ぎると一斉に売られて値段が下がりやすい傾向があるのです。せっかく優待をもらっても、それ以上に株価が下がって損をしてしまっては、元も子もありません。
そこで登場するのが、今回ご紹介する「クロス取引」という、ちょっと特別なテクニックです。これは「つなぎ売り」とも呼ばれ、株価の上がり下がりによる損得をほぼゼロにしながら、株主優待の権利だけを安全に手に入れるための方法です。この記事では、株の初心者さんでも安心して挑戦できるよう、この魔法のようなテクニックの全てを、どこよりも分かりやすく解説していきます。
ちなみにですが私と、最近教えてやり始めた妻も時々このクロス取引をして株主優待をもらって優待生活を楽しんでます。
第1章:「優待だけゲット」の魔法、クロス取引って何?
クロス取引のすごいところは、株価が上がっても下がっても自分の資産に影響が出ないように「保険」をかけられる点にあります。その仕組みをのぞいてみましょう。
1.1. 値動きを”無効化”する仕組み
クロス取引とは、とてもシンプルに言うと、同じ会社の株を、同じ数だけ「買う」注文と「借りてきて売る」注文を同時に出すことです。
これをすると、まるでシーソーの両端に同じ重さの荷物を置いたように、バランスが取れて値動きの影響を受けなくなります。
- 株価が下がると…
- 「買った」株では損が出ます。
- でも、「借りて売った」株では全く同じ額の利益が出ます。
- 結果:プラスマイナスゼロ!
- 株価が上がると…
- 「買った」株では利益が出ます。
- でも、「借りて売った」株では全く同じ額の損が出ます。
- 結果:やっぱりプラスマイナスゼロ!
このように、株価がどう動いても損も得もしない状態を作り出し、その間に株主優待をもらう権利だけをちゃっかり確保するのが、クロス取引の狙いです。優待をもらう締切日を過ぎると株価が下がりやすい、という 予測可能 な値動きから資産を守るための、非常に賢い防衛策なのです。
1.2. 魔法をかける3つのステップ
実際にクロス取引を行う手順は、たったの3ステップです。
- ステップ1:同時に注文!
優待が欲しい会社の「この日までに株を持っていればOK」という締切日(またはそれより前)に、「普通に買う」注文と「借りてきて売る」注文を、同じ株の数だけ同時に出します。朝9時の取引開始前に両方の注文を出しておくと、同じ値段で売買が成立しやすく、完璧な保険になります。 - ステップ2:締切日をまたぐ
「買い」と「借りて売り」の両方の注文を持ったまま、締切日の取引終了時間(午後3時半)を過ぎるのを待ちます。この瞬間、あなたは株主としてカウントされるので、株主優待をもらう権利が確定します。 - ステップ3:後片付けは「現渡し」で 締切日の翌日以降に、後片付けをします。このとき使うのが「現渡し(げんわたし)」という便利な方法。これは、 借りていた株を、自分が「普通に買った」株でそのまま返す手続きのことです。多くの証券会社ではこの手続きの手数料が無料で、市場で売買する必要がないため、最後まで値動きを気にすることなく取引をきれいに終えられます。
第2章:魔法にかかる費用は?コストを全部見せます
クロス取引は株価の変動リスクをなくせますが、残念ながら完全にタダではありません。でも、かかる費用をきちんと計算して、もらえる優待の価値がそれを上回っていれば問題ありません。
2.1. 基本料金:株のレンタル料「貸株料」
クロス取引で一番メインになる費用が、株を借りるためのレンタル料、「貸株料(かしかぶりょう)」です。計算方法は以下の通りです。
レンタル料=売買した金額×年間の料率×借りた日数÷365日
ここで大事なのは「借りた日数」の数え方。株を借りた日から返す日までの期間で、土日や祝日も全部日数に含まれるので注意が必要です。
【レンタル料の計算例】
- 株: 1株5,000円の株を100株(合計50万円分)
- 料率: 年3.9%とします
- 期間: 締切日(火曜日)に借りて、翌日(水曜日)に返します(2日間とカウント)。
- 計算式: (50万円×3.9%×2日)÷365日≈107円
この場合、かかる費用は約107円。缶ジュース1本分くらいのコストで優待が手に入るイメージです。もちろん、長く借りればその分だけ費用は増えていきます。
2.2. 要注意!配当金が出る株の「隠れコスト」
もしクロス取引をする株が配当金を出す場合、「配当落調整金」という少し厄介なコストが発生します。これは初心者の方がつまずきやすいポイントですが、仕組みは単純です。
- なぜ発生するの?: あなたは「普通に買った」株を持っているので、会社から配当金がもらえます。しかしその一方で、「借りてきて売った」株の本来の持ち主は、あなたに株を貸したせいで配当金がもらえなくなってしまいます。その穴埋めとして、あなたが配当金と同じ額を支払う義務を負うのです。
- なぜコストになるの?: 問題は、もらえる配当金と支払う金額に「税金の差」があることです。
- もらえる配当金: 税金(20.315%)が引かれた後の金額が振り込まれます。
- 支払う金額: 税金が引かれる前の満額(100%)を支払わなければなりません。
【隠れコストの計算例】
- 配当: 1株100円の配当で100株持っている場合、配当金は10,000円です。
- もらえる額: 10,000円−税金約2,031円=7,969円
- 支払う額: 10,000円
- あなたの負担: 7,969円(もらい)−10,000円(支払い)=−2,031円
この差額の2,031円が、あなたの実質的なコストになります。ですから、配当金が出る株でクロス取引をするときは、優待の価値からこの隠れコストを差し引いても、まだお得かどうかを判断する必要があります。
第3章:絶対に間違えてはいけない!安全な「借り方」の選び方
クロス取引で株を「借りてきて売る」とき、実は2つの方法、「一般信用」と「制度信用」があります。この選択を間違えると大変なことになる可能性があるので、しっかり理解しておきましょう。
3.1. 決定的な違い:予測不能なペナルティ料金「逆日歩」
二つの方法の最大の違いは、「逆日歩(ぎゃくひぶ)」という予測不能なペナルティ料金が発生するかどうかです。
逆日歩とは、危険な方のやり方(制度信用)で、みんなが一斉に同じ株を借りて売ろうとした結果、貸し出すための株が足りなくなってしまったときに発生する、追加のレンタル料のことです。人気の優待株では、この逆日歩がとても発生しやすくなります。
逆日歩の一番怖いところは、取引をしている最中には金額が分からず、後になってから「今回は1株あたり〇〇円です」と発表されることです。時には、もらえる優待の価値をはるかに超える高額な請求が来て、大損してしまう危険があるのです。
3.2. だからクロス取引は「一般信用」一択!
この恐ろしい逆日歩リスクを完全に避けることができる唯一の方法が、安全な方のやり方である「一般信用」を選ぶことです。一般信用の最大のメリットは、逆日歩が絶対に発生しないという点にあります。
一般信用は、証券会社が自分で確保している株を貸し出してくれるサービスです。そのため、貸し出し用の株がなくなれば取引はできませんが、後から予想外の請求が来ることは絶対にありません。レンタル料(貸株料)は少しだけ高めですが、コストが事前に確定できる安心感は何物にも代えがたいメリットです。
結論:株主優待のためのクロス取引では、必ず「一般信用」を使いましょう!
| 比較項目 | 危険な方法(制度信用) | 安全な方法(一般信用) |
|---|---|---|
| 逆日歩リスク | あり(予測不能・高額請求の危険) | なし |
| レンタル料 | 少し安い | 少し高いが、料金は確定していて安心 |
| 借りられる株 | 取引所が選んだ株 | 証券会社が独自に選んだ株 |
第4章:メリット・デメリットと成功のためのコツ
クロス取引の仕組みが分かったところで、改めてその良い点と気をつけるべき点、そして成功率を上げるためのコツを見ていきましょう。
4.1. 最大のメリット:株価の嵐から逃れられる
クロス取引の一番の魅力は、世の中の景気や株価の動きを一切気にすることなく、株主優待という「実り」だけを安全に収穫できることです。市場が大荒れの日でも、あなたの資産は守られています。この「確実性」が、クロス取引の最大の強みです。
4.2. 気をつけることと、その対策
もちろん、気をつけるべき点もあります。
- うっかりコスト倒れ: もらえる優待の価値が低いのに取引をして、レンタル料などの費用の方が高くついてしまう。
- 対策: 取引の前に必ずコストを計算し、本当にお得か確認するクセをつけましょう。
- 注文ミス: 「買い」と「売り」の株数を間違えたり、片方の注文を出し忘れたりする。
- 対策: 注文を出す前に、指差し確認!「銘柄、OK!」「株数、OK!」と声に出してみましょう。証券会社によっては、ミスを防ぐための専用注文機能もあります。
- 意外とお金がかかる: 株を「買う」ためのお金と、「借りて売る」ための担保のお金(約定金額の3割程度、最低30万円)の両方が必要になります。
- 対策: 最初は株価が安い銘柄で練習して、どれくらいのお金が必要になるか体感してみましょう。
4.3. 人気優待は争奪戦!「在庫切れ」との戦い方
安全な「一般信用」の唯一にして最大の弱点が、「在庫切れ」です。人気の優待株は、締切日が近づくと貸し出し用の株があっという間になくなり、取引したくてもできなくなってしまいます。
この問題への最も有効な対策は、複数の証券会社の口座を持っておくことです。A証券では在庫がなくても、B証券やC証券にはまだ残っている、ということがよくあります。お店によって品揃えが違うのと同じで、アクセスできる窓口を増やしておくことが、お目当ての優待を手に入れるチャンスを広げる鍵になるのです。
結論:さあ、魔法を使ってみよう!始める前の最終チェック
クロス取引は、株価の心配をせずに優待を楽しめる、とても賢い方法です。最後に、取引を始める前のチェックリストを確認しましょう。
- 必ず「一般信用」で!
予測不能な高額請求(逆日歩)を避けるため、株を借りるときは必ず安全な「一般信用」を選びましょう。 - コスト計算は絶対!
もらえる優待の価値が、かかる費用(レンタル料や隠れコストなど)をちゃんと上回っているか、事前に計算しましょう。 - 証券口座は複数用意!
人気優待の「在庫切れ」に備えて、いくつかのネット証券(SBI証券、楽天証券、松井証券、マネックス証券、SMBC日興証券など)に口座を開いておくとチャンスが広がります。 - 注文内容は何度も確認!
注文ミスは大きな損につながる可能性があります。「銘柄」「株数」「注文の種類」を、送信ボタンを押す前にもう一度チェックしましょう。 - まずは練習から!
最初のうちは、株価が安くてコストも少なくて済む銘柄で一連の流れを体験してみましょう。自信がついたら、本命の優待に挑戦です。
これらのルールを守れば、クロス取引はあなたの投資ライフをより豊かで楽しいものにしてくれるはずです。このガイドを片手に、ぜひ賢い優待生活をスタートさせてください。
松井証券ではじめてみる
マネックス証券ではじめてみる
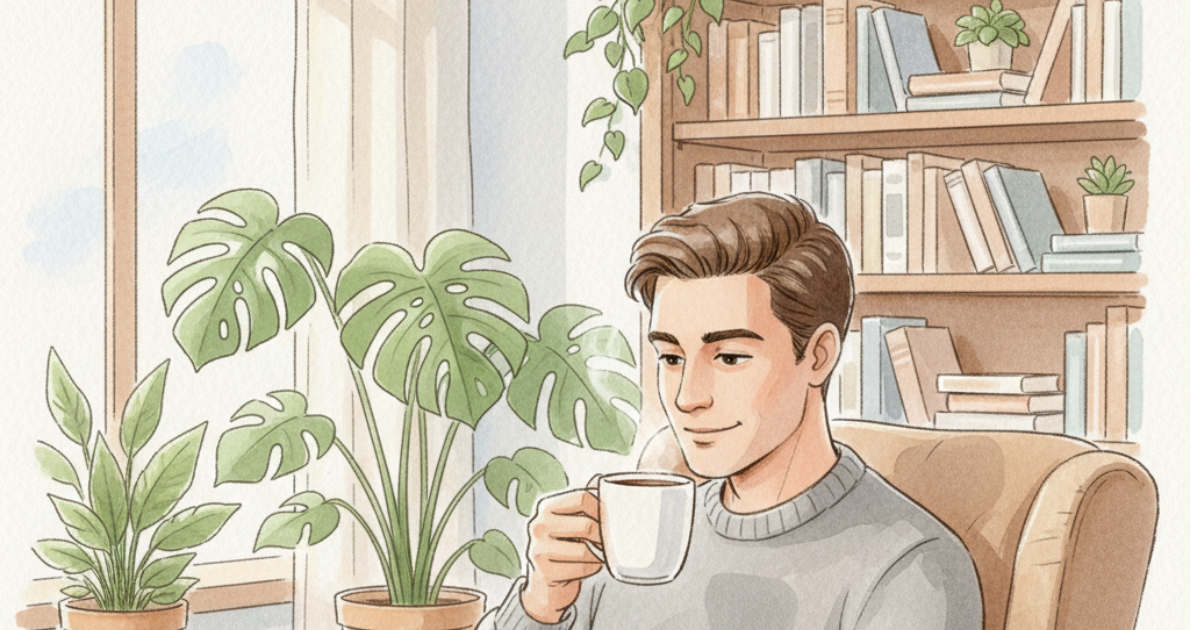
コメント